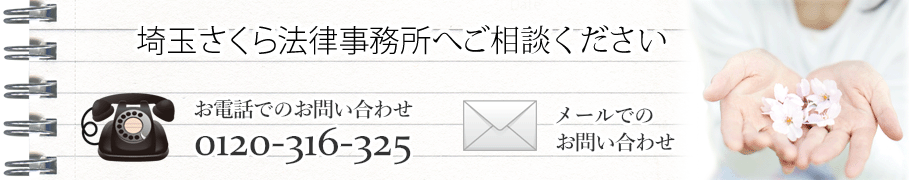相続に関する問題は埼玉さくら法律事務所へご相談ください
埼玉さくら法律事務所トップページ > 取扱業務・個人のお客様 > 相続
相続
「相続に関する紛争」というと、自分には、関係ないとお思いではないでしょうか?
「まだ、先のことだから」
「子どもたちで決めてもらえばいい」
「自分には、大した財産がないから大丈夫」
などと思ってはいないでしょうか?
しかし、裁判所が集めたデータである「司法統計」によると、平成23年に裁判所に新たに起こされた遺産分割に関する争い(遺産をどのように分けるかという争い)は1万3000件余りです。
現実には、これだけの紛争が起こっています。
相続に関する紛争は、誰にでも起こりうるものといっていいでしょう。
誰にでも起こりうる「相続に関する紛争」ですが、それを解決するのは容易ではありません。
相続人は誰か、相続財産はどれだけあるのか、相続財産をどのように分けるのか等、解決すべき問題はたくさんあります。
そして、これらの問題は、法律によって一刀両断できるものではなく、感情論がからみ複雑なものとなります。
当事務所では、依頼者にとって、どのような解決方法が一番いいのか、というのを依頼者に寄り添って考え、一緒に解決していきます。
まずは、当事務所まで、お気軽にご相談ください。
「まだ、先のことだから」
「子どもたちで決めてもらえばいい」
「自分には、大した財産がないから大丈夫」
などと思ってはいないでしょうか?
しかし、裁判所が集めたデータである「司法統計」によると、平成23年に裁判所に新たに起こされた遺産分割に関する争い(遺産をどのように分けるかという争い)は1万3000件余りです。
現実には、これだけの紛争が起こっています。
相続に関する紛争は、誰にでも起こりうるものといっていいでしょう。
誰にでも起こりうる「相続に関する紛争」ですが、それを解決するのは容易ではありません。
相続人は誰か、相続財産はどれだけあるのか、相続財産をどのように分けるのか等、解決すべき問題はたくさんあります。
そして、これらの問題は、法律によって一刀両断できるものではなく、感情論がからみ複雑なものとなります。
当事務所では、依頼者にとって、どのような解決方法が一番いいのか、というのを依頼者に寄り添って考え、一緒に解決していきます。
まずは、当事務所まで、お気軽にご相談ください。
1、遺言の種類について
〈1〉自筆証書遺言とは
遺言者が、遺言書の全文・日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。
遺言者が、遺言書の全文・日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。
〈2〉公正証書遺言とは
2人以上の証人の立会いを得て、遺言者が公証人に遺言の趣旨を伝え、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印し、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印することによって成立する遺言です。
2人以上の証人の立会いを得て、遺言者が公証人に遺言の趣旨を伝え、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印し、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印することによって成立する遺言です。
それぞれのメリット・デメリット
| 自筆証書遺言 | |
| メリット | デメリット |
| ・手軽で費用が かからない。 ・書き直しが簡単。 |
・自分で書くので、 内容的に不備が生じやすい。 ・家庭裁判所による検認手続が必要。 |
| 公正証書遺言 | |
| メリット | デメリット |
| ・公証人が作成するので、 内容的に明確となる。 ・家庭裁判所による検認手続が不要。 |
・作成費用がかかる。 ・秘密が利害関係人に 知られるおそれがある。 |
〈3〉
遺言には、この他に「秘密証書遺言」「危急時遺言」「隔絶地遺言」などがあります。
遺言には、この他に「秘密証書遺言」「危急時遺言」「隔絶地遺言」などがあります。
2、遺言作成費用について
| 定型の遺言書 | 15万円 |
| 非定型の遺言書 | 経済的利益の額 | 費用 |
| 300万円以下 | 20万円 | |
| 300万円超 3000万円以下 |
1%+17万円 | |
| 3000万円超 3億円以下 |
0.3%+38万円 | |
| 3億円超 | 0.1%+98万円 |
3、遺言書保管費用について
| 年間 5,000円 ※消費税別 |
公正証書遺言の場合は、公証人役場に保存されるため、紛失や改変のおそれはありません。
しかし、自筆証書遺言の場合には、保管場所によっては、紛失や改変のおそれがあります。
また、場合によっては、誰にも見つけられずに、相続がなされるおそれもあります。
そこで、当事務所では、遺言書保管サービスを行っています。弁護士は、守秘義務を負っていますので、遺言の内容を第三者に漏らすということは絶対にありません。
また、弁護士に遺言書の保管を依頼しておけば、亡くなられたときに、その後の相続手続がスムーズに進みます。
しかし、自筆証書遺言の場合には、保管場所によっては、紛失や改変のおそれがあります。
また、場合によっては、誰にも見つけられずに、相続がなされるおそれもあります。
そこで、当事務所では、遺言書保管サービスを行っています。弁護士は、守秘義務を負っていますので、遺言の内容を第三者に漏らすということは絶対にありません。
また、弁護士に遺言書の保管を依頼しておけば、亡くなられたときに、その後の相続手続がスムーズに進みます。
4、遺言執行費用について
| 経済的利益の額 | 費用 |
| 300万円以下 | 30万円 |
| 300万円超3000万円以下 | 2%+24万円 |
| 3000万円超3億円以下 | 1%+54万円 |
| 3億円超 | 0.5%+204万円 |
遺言は、それを作成しても、自動的に相続手続が進んでいくわけではありません。
遺言の内容を実行していくために、遺言執行という手続が必要になります。
しかし、相続財産を適正に管理し、執行していくことは容易ではありません。
そこで、当事務所では、専門家である弁護士が遺言執行者となり、遺言の内容を実行いたします。
遺言の内容を実行していくために、遺言執行という手続が必要になります。
しかし、相続財産を適正に管理し、執行していくことは容易ではありません。
そこで、当事務所では、専門家である弁護士が遺言執行者となり、遺言の内容を実行いたします。
1、相続人の順位について
相続に関しては、誰が優先的に相続人になるのかという順位があります。
〈1〉第一順位
被相続人(亡くなった方)に子どもがいる場合、その子どもが第1順位の相続人となります。
※なお、被相続人の子どもが、相続の開始以前に亡くなっていた場合や相続の欠格・廃除によって相続権を失ったときは、その者の子どもが代襲相続します
被相続人(亡くなった方)に子どもがいる場合、その子どもが第1順位の相続人となります。
※なお、被相続人の子どもが、相続の開始以前に亡くなっていた場合や相続の欠格・廃除によって相続権を失ったときは、その者の子どもが代襲相続します
〈2〉第二順位
第1順位の相続人がいない場合、被相続人の直系尊属(両親、祖父母など上の世代)が相続人となります。
直系尊属が複数存在する場合は、その親等が近い者が相続人となります(両親、祖父母の間では、両親。)。
第1順位の相続人がいない場合、被相続人の直系尊属(両親、祖父母など上の世代)が相続人となります。
直系尊属が複数存在する場合は、その親等が近い者が相続人となります(両親、祖父母の間では、両親。)。
〈3〉第三順位
第1順位、第2順位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
※兄弟姉妹の場合は、その子どもについてのみ代襲相続が発生します。
第1順位、第2順位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
※兄弟姉妹の場合は、その子どもについてのみ代襲相続が発生します。
〈4〉
配偶者は、これらの順位に関わらず、常に相続人となります。
配偶者は、これらの順位に関わらず、常に相続人となります。
2、相続放棄について
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。
相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人ではなかったことになります。
したがって、相続放棄をした者がいないかを調査する必要があります。
相続放棄をした場合は、家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書の交付を受けることができます。
相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人ではなかったことになります。
したがって、相続放棄をした者がいないかを調査する必要があります。
相続放棄をした場合は、家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書の交付を受けることができます。
3、相続の欠格・排除について
1、相続欠格
被相続人を殺害したり、遺言書を偽造するなど一定の欠格事由に該当する者は相続人となることができません。
被相続人を殺害したり、遺言書を偽造するなど一定の欠格事由に該当する者は相続人となることができません。
2、相続人の排除
被相続人に対し虐待や重大な侮辱を加えたり、その他著しい非行があった者について、被相続人は、家庭裁判所に、その者の廃除を請求することができます。
そして、家庭裁判所によって廃除の審判がなされると、その者は相続人となることができません。
被相続人に対し虐待や重大な侮辱を加えたり、その他著しい非行があった者について、被相続人は、家庭裁判所に、その者の廃除を請求することができます。
そして、家庭裁判所によって廃除の審判がなされると、その者は相続人となることができません。